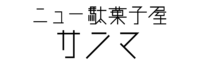ごあいさつ
はじめまして。ニュー駄菓子屋サンマ店長の村上天悠と申します。
ニュー駄菓子屋サンマを開業した経緯についてお話します。少し長くなりますが、どうぞお付き合いください。
移住先で感じた、子どもの居場所の少なさ
私は神奈川県で生まれ、幼少期~青年期を埼玉県、20代を中野区で暮らし、30歳で奥多摩町へと移住してきました。
豊かな自然、ゆったりと流れる時間、都心からのアクセスの良さが奥多摩町を移住先に選んだ理由です。
河原で焚き火したり、山で自然散策したり、地域のイベントに参加したりと移住生活を満喫する一方で、気になることがありました。
それは、子どもの遊び場が地域にほとんど見当たらないということです。
最初にそう感じたのは、近所のフリーマーケットに出展したときのこと。
このフリマでは町外から駄菓子屋さんが出展されていたのですが、子どもたちは何時間も楽しそうに駄菓子を眺めて過ごしていました。
「駄菓子でそこまで楽しめるものか」
はじめはそんな風に感じたものの、よくよく考えてみると、町内には子どもが小遣いを持って遊びに行けるような場所がほとんどないことに気づきました。
私自身のことを振り返ってみると、児童期・思春期は駄菓子屋や古本屋、スーパーのお菓子コーナー、デパートのゲームコーナーなどによく出入りし、その中で金銭感覚や対人関係、文化、教養など様々なものを身に付けることができたと思っています。
「奥多摩町の子どもは、こうした社会経験を得られるのだろうか」
そんな疑問を抱くようになりました。
子どもにとってのサード・プレイスの重要性
移住後しばらく経って、私は小学生の放課後居場所づくり事業に携わるようになります。
地域の子どもたちと日常会話を重ねる中で知ったのは、生活の大部分が家と学校との往復で完結しているという事実でした。
保護者に車で学校まで送ってもらい、放課後を学童で過ごして、保護者に車で学校まで迎えにきてもらう。
町域が広いという地域特性から、どうしても子どもの移動が保護者の車に依存せざるを得ない状況があるのだろうと感じます。
世間では、家でも学校でもないサード・プレイス(第3の場)の重要性が説かれるようになりました。子どもにいたっては、サード・プレイスが多いほどが幸福感や自己肯定感、チャレンジ精神や将来への希望までも高まることがデータから明らかになっています。
奥多摩町にも、子どもたちが自分の足で行けるサード・プレイスがあったらいいと考えるようになりました。
子どもが子どもでいられる時間は、あっという間
私はとある自治体で、子どもの権利関連の事業に携わっています。
その事業では中高生が行政に、まちづくりに関して意見するのですが、とある高校生からこんな発言がありました。
「まちに私たちの居場所をつくってください。私たちが学生でいられる時間はあと数年しかありません。」
「○年計画と時間がかかることは理解していますが、その頃に私は学生でなくなっています。今すぐつくってください。」
なるほどなと思いました。
行政が予算を付けて、計画を立てて、施工が終わるまでには長い年月がかかります。
僕自身も、奥多摩町の子どものサード・プレイスづくりを役場に期待しようと思っていた部分がありましたが、その頃には今現在関わっている子どもたちは大人になってしまうでしょう。
移住して感じたこと、子どもの言葉、これらのピースが少しずつ合わさっていきます。
ちょうどこの頃、奥多摩駅徒歩5分に賃貸で戸建ての空き家があることを知りました。
ここなら、近所の小学校や中学校から歩いて来られる距離感です。
「ないなら、自分でつくればいい」
サンマの由来は「仲間」「空間」「時間」からなる三つの間のこと。
地域の子どもにとってのそんな場をつくるぞと、ほとんど勢いで決心しました。
人口減少地域でも、持続可能な空間を目指して
サード・プレイスをつくるにあたって最初に考えたのは、
「子どもが行きたくなる空間、気軽に行ける空間って?」
ということでした。
脳裏に浮かんだのは、フリマで見かけた駄菓子の前で何時間も楽しそうにしている子どもたちの姿です。
一方、少子化が進む中で駄菓子屋がビジネスモデルとして難しいことも分かり切った事実です。
駄菓子屋がしたい。しかし、それだけでは収益が厳しい。そこでカフェ機能や参画機能もサンマのサービスに加えました。
地域の大人や観光の方、みんなにお店を利用してもらうことで、子どものサード・プレイスを運営していく。そんな想いからコンセプトを「みんなで営むパブリック」に決めました。
店内に子ども発案のコーナーを設けたり、地域の皆さんに懇親会の場として利用いただいたり、イベントを企画・開催していただいたりと、少しずつ思い描いていたものが形になっていく手応えを感じています。
サンマのこれから
ニュー駄菓子屋サンマは、これからどんどんおもしろい場になっていく気がしています。
実際問題、私自身の中にある「こうしていきたい」というイメージと、利用者の皆さんが描く「こう利用していきたい」というイメージとが混ざり、重なり、想定していない未来に日々直面しているからです。
店主である私自身、この店がどう変化していくのかドキドキとワクワクでいっぱいです。
この文章を読んでいただいた皆さまには、ぜひ何らかの形でニュー駄菓子屋サンマに関わっていただき、この場を共に育んでいってもらえるとうれしいです。
子どもたちがたのしく過ごせる地域を、ひいては世の中を、一緒につくっていきましょう。